
はじめに
「この牛肉、『名誉賞受賞』って書いてあるけど、普通の和牛と何が違うの?」
そんな疑問を持たれたことはありませんか?
牛肉の世界には、一般の消費者にはあまり知られていない「品評会」という世界があります。その中でも「全国肉用牛枝肉共励会」における「名誉賞」は、畜産農家にとって生涯をかけて目指す最高峰の栄誉なのです。
この名誉ある賞の真の価値と意義について、正確な情報をもとにご説明いたします。
『さつま福永牛オンラインショップ』はこちら
『熟成焼肉Gyudo!本店』の御予約はこちら
『個室焼肉 牛道はなれ』の御予約はこちら
全国肉用牛枝肉共励会とは
共励会の概要
全国肉用牛枝肉共励会は、年に一度開催される日本で最大規模の牛肉の品評会です。市場取引の活性化、生産者の生産意欲の高揚などを目的として、優秀な和牛を集めて、枝肉の品質を競う共励会として開催されています。
開催概要
- 開催場所:東京都中央卸売市場食肉市場
- 主催:東京食肉市場協会と東京食肉市場
- 出品規模:全国32道府県から和牛、交雑牛500頭が出品
共励会の位置づけ
各ブランド牛で共励会を開くなど、様々な条件でこの共励会は開かれていますが、その中でも、すべてのブランド牛が対象となっており、全国から選りすぐりの牛肉が集まる、最大の共励会がこの「全国肉用牛枝肉共励会」です。
つまり、松阪牛、神戸牛、米沢牛といった有名ブランド牛も、地域ブランド牛も、すべて同じ土俵で競い合う、真の「日本一決定戦」なのです。
名誉賞の意味:最高位の栄誉
名誉賞とは何か
最高賞である「名誉賞」は、全国肉用牛枝肉共励会における最も権威ある賞です。この賞は単年度の優秀さだけでなく、継続的な excellence を示す農家に与えられる特別な栄誉です。
賞の序列
共励会には以下のような賞の序列があります:
- 名誉賞:最高位
- 最優秀賞:各部門(和牛去勢、和牛雌、交雑種)の最優秀
- 優秀賞:上位入賞
- 優良賞:入賞
経済的価値
名誉賞受賞牛の経済的価値は圧倒的です。実際の取引例を見ると:
- 共励会に出した時の枝肉価格は1kgあたり16,885円(川村ファームの仙台牛)
- 同日のせりで1キロ1万3586円の高値で落札(松永牧場)
- キロ単価1万1,111円で小川畜産興業が購買(佐々木敏朗氏の宮城県産)
通常の和牛がキロ当たり2,000円~3,000円程度で取引されることを考えると、名誉賞受賞牛は5倍以上の価格で取引されることがわかります。
近年の受賞実績と傾向
近年の名誉賞受賞者
令和5年(2023年) 宮城県の髙橋榮一氏の出品牛(黒毛和種去勢、31カ月齢、A5、枝肉重量498.0kg、歩留基準値78.7、BMS12)が名誉賞に輝いた。キロ単価8106円で小川畜産興業(株)が落札した。宮城県勢が5年連続で名誉賞を獲得
令和4年(2022年) 令和4年度全国肉用牛枝肉共励会にて最高位の名誉賞を受賞(株式会社松永牧場・島根県)昨年に続く連覇を達成
令和3年(2021年) 島根県の松永牧場(益田市)の出品牛(和牛去勢)が最高位の名誉賞を受賞
令和元年(2019年) 宮城県の(株)川口ファームが出品した黒毛和種去勢牛(父「第1花国」母の父「安福久」)が輝き、同共励会史上過去最高のキロ単価2万7,001円で(株)ふじなわがせり落とした
平成29年・30年(2017年・2016年) 「2017年全国肉用牛枝肉共励会」「2016年全国肉用牛枝肉共励会」において、「川村ファーム」の仙台牛が、全国から選りすぐりの500頭の中から、最高賞である「名誉賞」を受賞
平成27年(2015年) 喜多方市の株式会社湯浅ファームさんが出品した「福島牛」が最高位の名誉賞を受賞
平成25年(2013年) 鹿児島県さつま町の有限会社福永畜産が出品した「さつま福永牛」が最高位の名誉賞を受賞
血統と技術の傾向
血統の特徴 名誉賞受賞牛の血統は、父が次世代エースとして注目を集める「福之鶴」、母の父が「美国桜」、母の祖父が「北乃大福」。2代祖が「安福久」以外の牛が名誉賞を獲得するのは12年ぶり
格付けと体格 32カ月齢で、枝肉重量631キロ、格付けはA5、BMSナンバー12
これらのデータから、名誉賞受賞牛は:
- 最高格付けのA5等級
- BMSナンバー12(最高レベルの霜降り)
- 適切な枝肉重量(600kg前後)
- 優秀な血統
という条件を満たしていることがわかります。
畜産農家が名誉賞を目指す理由
技術者としての誇り
松永牧場の松永拓磨さん(35)は「おいしさを一番に、長年重視してきた脂の質が評価された」と喜んだ
この言葉が示すように、名誉賞受賞は畜産農家にとって自らの技術が日本最高水準であることの証明です。何十年もかけて培ってきた飼育技術、血統管理、品質へのこだわりが認められる瞬間なのです。
経営への影響
ブランド価値の向上 名誉賞受賞により、その農家の牛肉は全国的に認知され、ブランド価値が飛躍的に向上します。
継続的な高値取引 一度名誉賞を受賞すると、その農家の牛肉は継続的に高値で取引されるようになります。2年ぶり3回目の受賞という表現からもわかるように、優秀な農家は繰り返し入賞することが多く、安定した高収益を実現できます。
技術継承への動機 このような素晴らしい賞をいただけたこと、この牧場に携わってくださる皆様に感謝という受賞者のコメントからもわかるように、名誉賞受賞は農家にとって技術継承への強い動機となります。
業界全体への貢献
技術向上の牽引 名誉賞受賞農家の技術は業界全体の目標となり、全体的な技術向上を促進します。
消費者への価値提供 最高品質の和牛を市場に供給することで、消費者により良い食体験を提供します。
日本の畜産業の地位向上 国際的にも注目される品質レベルを維持することで、日本の畜産業の地位向上に貢献します。
審査基準と評価の厳格さ
枝肉格付けの基準
さしの量が高位平準化する中、脂の質やさしの細かさ、歩留まりの評価が高い枝肉が上位入賞する傾向が目立った
これは、単に霜降りが多いだけでなく、以下の要素が重要であることを示しています:
脂の質
- 融点の低さ(口溶けの良さ)
- 色艶の美しさ
- 香りの良さ
さしの細かさ
- 均等で細かい霜降りの分布
- 赤身と脂身のバランス
歩留まり
- 一頭の牛から取れる食肉の割合
- 経済性の指標
審査の客観性
審査は日本食肉格付協会の格付員によって行われ、極めて客観的で厳格な基準に基づいています。感情や主観が入り込む余地のない、科学的で公正な評価システムです。
名誉賞受賞牛の特徴
肉質の特徴
1級フードアナリストとして名誉賞受賞牛を評価すると、以下の特徴があります:
外観
- 美しく均等な霜降り
- 鮮やかで理想的な肉色
- 脂肪の純白性と光沢
食感
- 口に入れた瞬間の柔らかさ
- 脂の融点の低さによる口溶け
- 適度な歯ごたえと弾力性
味わい
- 深いコクと旨味
- 上品で甘い脂の風味
- 後味の良さ
香り
- 肉本来の豊かな香り
- 脂の上品な香り
調理適性
名誉賞受賞牛は、どのような調理法でもその真価を発揮しますが、特に:
ステーキ 最高品質の証明として、シンプルな塩焼きで素材の良さを堪能
すき焼き 上質な脂が甘辛いタレと絶妙に調和
しゃぶしゃぶ 繊細な肉質と脂の質の良さを実感
消費者にとっての価値
特別な食体験
名誉賞受賞牛を口にすることは、単なる食事を超えた特別な体験です:
日本最高峰の技術の結晶 何十年もの経験と技術の蓄積
生産者の情熱 牛一頭一頭への愛情と責任感
日本の食文化 和牛という世界に誇る文化の頂点
購入時の確認ポイント
証明書や表示
- 共励会での受賞歴の明記
- 生産者名の表示
- 個体識別番号
信頼できる販売店
- 生産者との直接取引
- 適切な温度管理
- 専門知識を持つスタッフ
まとめ:名誉賞の真の価値
名誉賞受賞の和牛は、単に美味しい牛肉というだけではありません。それは:
日本の畜産技術の最高峰
長年にわたって蓄積された技術と経験、そして絶え間ない改良への努力の結晶です。
生産者の情熱と誇り
おいしさを一番に、長年重視してきた脂の質が評価されたという言葉に表されるように、生産者の真摯な取り組みと情熱の証です。
日本の食文化の象徴
世界に誇る和牛文化の頂点に位置する、特別な存在です。
持続可能な農業の証
環境と調和しながら最高品質を追求する、理想的な農業の姿を示しています。
「名誉賞受賞」の表示を見かけたら、それは日本の畜産業界最高峰の技術と情熱が込められた、世界でも類を見ない特別な牛肉なのだということを思い出してください。
その一口一口に、生産者の物語と日本の農業技術の粋が込められているのです。きっと、普通の牛肉では味わえない感動を体験できることでしょう。
『さつま福永牛オンラインショップ』はこちら
『熟成焼肉Gyudo!本店』の御予約はこちら
『個室焼肉 牛道はなれ』の御予約はこちら
参考文献
¹ 東京食肉市場株式会社(2024)「共励会・共進会結果」 https://ssl.tmmc.co.jp/kyourei-kyoushin/commendation/
² 日本農業新聞(2023)「松永牧場(島根)が連覇 全国肉用牛枝肉共励会」 https://www.agrinews.co.jp/news/index/192586
³ 福島県(2023)「全国レベルの共励会で「福島牛」が最高位を獲得」 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36035d/fukushimagyuukyoureikaijushou.html
⁴ 畜産日報(2019)「第21回全農肉牛枝肉共励会結果」 https://www.ssnp.co.jp/news/meat/2019/07/2019-0709-1336-14.html
【筆者プロフィール】 福永(株式会社牛道役員) 1級フードアナリスト 和牛業界に携わる中で、全国の優秀な畜産農家とのネットワークを築く。品評会の審査基準や業界動向に精通し、消費者と生産者を結ぶ架け橋として活動している。


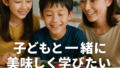
コメント