
はじめに
飛行機の窓から見える桜島の雄大な姿が、だんだん小さくなっていく‥。東京へ向かう機内で、私はいつも同じことを考えます。
「今度は、どんな方に故郷の味を届けられるだろうか」
鹿児島県さつま町で生まれ育った「さつま福永牛」が、なぜ遠く離れた東京まで旅をするのか。今日は、その理由について、率直にお話しさせていただきたいと思います。
牛たちの故郷:さつま町の記憶
ホタルが舞う夜の思い出
牛たちが育った鹿児島県薩摩郡さつま町。北薩最高峰の紫尾山を仰ぎ見る、自然豊かなこの町には、都会では見ることのできない風景があります。
夏の夜、田んぼの上をふわりふわりと舞うホタルの光。そのホタルが群生するほど清らかな水が、この土地には豊富に湧いています。地元の人々は子どもの頃は当たり前だと思っていたこの環境が、実はとても特別なものだったのだと、大人になってから気づいたと話します。
この清らかな水と豊かな自然が、さつま福永牛の故郷です。
変わらない田園風景
別の仕事に就いていた私が、25年間毎日の通勤路で目にしていた一面の田園風景。季節ごとに表情を変える田んぼ、春にはむせるような梅の香、イチゴやお米を育てて活き活きと働く人々の姿。
この変わらない風景の中で、福永畜産の牛たちは今日も大切に育てられています。ストレスとは無縁の、のんびりとした時間が流れる環境。これこそが、さつま福永牛の美味しさの原点なのです。
なぜ東京なのか
「本物を知ってほしい」という願い
福永社長が東京食肉市場への挑戦を決めた時、周囲からは「なぜわざわざ遠い東京まで」「農協を離れて?」という声もありました。鹿児島には優秀な市場もあり、地元での販売も十分に可能だったからです。
しかし、福永社長の想いは違いました。
「本当に美味しい和牛を、一人でも多くの人に味わってもらいたい、バイヤーさんやレストランと直接繋がりたい」と。
その「一人でも多くの人」の中には、日本最大の消費地である東京の人々も含まれていたのです。故郷の自慢の牛肉を、より多くの方に知っていただきたい—その純粋な想いが、東京への扉を開いたのです。
鹿児島の畜産技術を全国へ
鹿児島県は、全国でも有数の畜産県です。温暖な気候と豊かな自然環境、そして生産者の高い技術力により、素晴らしい畜産物を生産しています。
しかし、その素晴らしさが全国に十分に伝わっているかというと、まだまだ課題があります。知名度の高い他産地のブランド牛に比べ、鹿児島の和牛の認知度はそれほど高くありません。
だからこそ、福永畜産のような生産者が東京に挑戦することで、鹿児島の畜産技術の高さを全国に発信する意味があるのです。
直営店「Gyudo!」という挑戦
三軒茶屋という選択
2012年、福永畜産は鹿児島天文館に直営焼肉店「Gyudo!」をオープンしました。そして数年後、ついに東京進出を果たします。その場所としてご縁があったのが、三軒茶屋でした。
なぜ三軒茶屋だったのか。銀座でも六本木でもなく、住宅街に近いその場所を選んだ理由—それは「地域に根ざしたお店にしたい」という想いがあったからです。
高級店として一部の人だけに愛されるのではなく、地域の人々に日常的に愛される店を目指したい。故郷・さつま町での地域密着の精神を、東京でも大切にしたかったのです。
生産者だからこそできること
直営店の最大の強みは、生産者だからこそ伝えられる「ストーリー」があることです。
どんな環境で、どんな想いで牛を育てているのか。なぜこの部位がおすすめなのか。どんな食べ方が一番美味しいのか。
そうした生産者ならではの情報を、お客様に直接お伝えできる。これは、卸売だけでは決してできないことです。お客様の「美味しい!」という笑顔を直接見ることができる。それが、生産者としての何よりの喜びなのです。
コロナ禍が教えてくれたこと
試練を乗り越えた先に見えたもの
2020年、新型コロナウイルスの影響で、飲食業界は大きな打撃を受けました。Gyudo!も例外ではありませんでした。一時は2店舗の閉店を余儀なくされ、厳しい状況に直面しました。
しかし、この困難な時期が、新たな可能性を教えてくれました。
「お店に来ていただけないなら、お客様のもとへ直接お届けしよう」
オンラインショップの充実、冷凍技術を活かした商品開発、全国配送システムの構築。これらの取り組みにより、物理的な距離を越えて、より多くの方にさつま福永牛をお届けできるようになったのです。
「おうち時間」への貢献
外出自粛期間中、多くの方が家庭での食事を見直すようになりました。「せっかく家で食べるなら、美味しいものを」という声が増えたのです。
このタイミングで、私たちは家庭での「特別な時間」を演出するお手伝いができるようになりました。瞬間冷凍技術により、故郷の味をそのまま全国のご家庭にお届けする。これは、コロナ禍が生み出した新しい価値だったのかもしれません。
東京で教わったこと
多様性という財産
東京で事業を展開することで、鹿児島にいては経験できない多くのことを学びました。
様々な地域出身の方々、異なる文化背景を持つ方々との出会い。それぞれの「美味しい」の基準や、食に対する価値観の違い。そうした多様性に触れることで、私たちの視野も大きく広がりました。
「鹿児島の常識」が「全国の常識」ではないことを知り、より多くの方に受け入れられる商品作りのヒントを得ることができたのです。
「伝える」ことの大切さ
東京では、さつま福永牛のことを知らない方がほとんどです。だからこそ、「なぜ美味しいのか」「どんな特徴があるのか」をしっかりと伝える必要があります。
この「伝える」経験が、私たちのコミュニケーション能力を大きく向上させました。専門用語を使わずに、誰にでも分かりやすく説明する。これは、故郷に戻ってからも大いに役立っています。
1級フードアナリストとしての使命
客観的な視点の重要性
家族経営の会社で働く立場として、どうしても主観的になりがちな部分があります。しかし、1級フードアナリストとしての専門的な知識と訓練により、客観的な視点を保つよう努めています。
東京という大消費地で、様々な産地の和牛と比較される環境に身を置くことで、さつま福永牛の本当の実力を冷静に評価することができます。そして、その評価に基づいて、自信を持って品質をお伝えすることができるのです。
食育の精神を商品に込めて
25年間の学校栄養教諭の経験で培った「食育」の精神は、現在の仕事にも大いに活かされています。
単に「美味しいから食べて」ではなく、「なぜ体に良いのか」「どんな栄養があるのか」「どう調理すれば家族みんなで楽しめるのか」—そうした教育的な観点も含めて、商品の価値をお伝えしています。
これからの展望
故郷と東京をつなぐ架け橋として
私たちの使命は、単に商品を売ることではありません。故郷・鹿児島の素晴らしさを、東京をはじめとする全国の皆様にお伝えすること。そして、その架け橋となることです。
さつま福永牛を通じて、鹿児島の自然の豊かさ、生産者の想い、地域の文化を感じていただけたら—そんな願いを込めて、日々の業務に取り組んでいます。
次世代への想い
現在、福永畜産では次世代への技術継承も重要な課題となっています。長年培ってきた「炊いた餌」の技術や、牛への愛情深いケアの方法を、確実に次の世代に引き継いでいかなければなりません。
東京での経験で得た知見も含めて、より良い牛作り、より良い商品作りを次世代に託していく。それが、現在の私たちの大切な責任だと感じています。
おわりに
鹿児島から東京へ—それは、物理的な距離以上に、大きな挑戦でした。
しかし、その挑戦を通じて私たちが学んだことは計り知れません。故郷の素晴らしさを再認識し、全国の皆様とのつながりを築き、そして何より、「本物の美味しさを届けたい」という想いを、より強く、より確かなものにすることができました。
桜島を背にして東京へ向かう機中で、私は今日も考えています。
「この故郷の味を通じて、どんな笑顔に出会えるだろうか」
福永社長の「たくさんの人に本当の美味しい和牛を味わってほしい」という想いと、私の「多くの人に本物の食の価値を知ってほしい」という願いが、これからも多くの方の食卓に喜びをもたらすことを信じています。
故郷の味を届ける理由—それは、食を通じて人と人とのつながりを作りたいから。
その想いは、きっとこれからも変わることはありません。
【筆者プロフィール】 福永(株式会社牛道役員) 鹿児島県出身。1級フードアナリスト・管理栄養士・栄養教諭・日本箸教育講師。 25年間の学校栄養教諭経験を経て

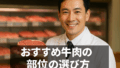
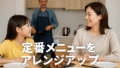
コメント