
なぜ牧場主が焼肉店を経営するのか?業界の常識を覆す理由
「なぜ牧場主が直接、焼肉店を経営するのですか?」
この質問を、来店されるお客様から頂くことがよくあります。確かに不思議に思われるかもしれません。通常、牧場で牛を育てる人と、お店で肉を提供する人は全く別の職業だからです。
しかし、この「当たり前」こそが、実は日本の畜産業界が抱える大きな問題の根源なのです。今回は、一般的な畜産業界の流通構造と、その中で失われてしまう「本当の価値」についてお話しします。
一般的な畜産業界の流通構造
複雑すぎる流通経路
多くの消費者の方は、牧場で育てられた牛がどのような経路を辿って食卓に届くのか、詳しくご存知ないかもしれません。実際の流通構造は、想像以上に複雑で多層的です。
一般的な和牛の流通経路
- 生産者(牧場) → 牛を育成・出荷
- 食肉市場 → 競りや相対取引
- 食肉卸業者 → 部分肉加工・流通
- 中間卸業者 → 地域別配送
- 小売業者・飲食店 → 最終消費者への販売
この過程で、牛一頭は少なくとも4-5の業者を経由します。それぞれの段階で、当然ながらマージンが発生し、牛が最終的に消費者の元に届く頃には、生産者の手を離れた時の価格の3-4倍になっていることも珍しくありません。
価格だけではない問題
しかし、価格の上昇以上に深刻な問題があります。それは情報の分断と品質管理の困難さです。
情報の分断
- どの牧場で育てられたのか
- どのような飼料で育ったのか
- どのような環境で飼育されたのか
- 生産者のこだわりや想い
これらの重要な情報が、流通過程で失われてしまいます。
品質管理の困難さ
- 個体別の肉質特性の把握困難
- 最適な熟成期間の判断不能
- 部位別の特徴を活かした調理法の伝達不可
- 品質低下のリスク増加
「規格化」という名の画一化
現在の流通システムでは、効率性を重視するあまり、すべての肉が「規格化」されてしまいます。A5ランク、A4ランクといった格付けは確かに一定の品質基準を示しますが、それだけでは表現しきれない肉の個性や特徴は無視されがちです。
例えば、同じA5ランクでも:
- MUFA値(一価不飽和脂肪酸)の含有量
- 脂肪の融点
- 筋繊維の細かさ
- 旨味成分の濃度
これらには大きな差があります。しかし、現在の流通システムでは、こうした細かな品質の違いを消費者に伝えることは困難です。
中間業者を通した品質劣化の現実
時間経過による劣化
牛肉は、と畜されてから消費者の口に入るまでの時間が長ければ長いほど、品質が劣化するリスクが高まります。
一般的な流通での日数
- と畜・解体:1-2日
- 食肉市場での滞留:2-3日
- 卸業者での加工・保管:3-5日
- 中間業者での配送・保管:2-3日
- 小売・飲食店での保管:1-3日
合計:9-16日
この間、肉は冷蔵状態で保管されますが、時間が経つにつれて:
- 水分の蒸発による重量減少
- 酸化による風味の劣化
- 色素の変化による見た目の劣化
- 細菌増殖のリスク増加
これらの問題が徐々に蓄積されていきます。
取り扱いの問題
また、多くの業者を経由する過程で、適切でない取り扱いが行われるリスクも増加します。
よくある問題
- 温度管理の不備
- 包装・梱包の不適切さ
- 異なる産地の肉の混在
- 部位の取り違え
熟成の機会損失
最も残念なのは、適切な熟成の機会を失うことです。
牛肉は適切な環境下で熟成させることで、旨味成分が増加し、肉質が格段に向上します。しかし、現在の流通システムでは、迅速な配送が優先され、熟成という付加価値を生む工程が軽視されがちです。
生産者が直接消費者に届けたい真の想い
「本当の美味しさ」を伝えたい
畜産に携わる者として、最も切ない思いは自分が育てた牛の本当の美味しさが消費者に届かないことです。
鹿児島県さつま町で福永畜産を営む福永充氏は、こう語っています:
「せっかく手間暇かけて育てた牛が、流通の過程で品質を落としてしまうのを見ているのは、本当に辛いことです。自分の牛の本当の美味しさを、お客様に味わってもらいたい。その一心で、この店を始めました」
顔の見える関係を築きたい
現在の流通システムでは、生産者と消費者の距離が遠すぎます。お客様は、自分が食べている肉がどのような環境で、どのような想いで育てられたのかを知ることができません。
一方、生産者も、自分の牛がどのような方に食べられ、どのような評価を受けているのかを知ることができません。
直営店舗だからこそ可能なこと
- 生産者の想いを直接お客様に伝える
- お客様の声を直接生産現場にフィードバック
- 牛の個体情報を詳細にお客様に提供
- 最適な調理法や食べ方をお客様にお伝え
持続可能な畜産業を目指したい
現在の価格競争中心の畜産業界では、品質向上よりもコスト削減が優先されがちです。しかし、これでは長期的に見て、日本の畜産業の発展は望めません。
6次化産業の理念 生産(1次)× 加工(2次)× 販売(3次)= 6次化
この掛け算の関係が示すように、どれか一つでもゼロになれば、全体の価値もゼロになってしまいます。生産から販売まで一貫して管理することで、それぞれの段階で最大限の価値を生み出すことができるのです。
お客様との共創による価値向上
直営店舗の最大の魅力は、お客様との対話を通じた価値創造です。
具体的な取り組み
- お客様の好みに合わせた部位の提案
- 季節や個体に応じた最適な熟成期間の調整
- お客様のフィードバックを活かした飼育改善
- 特別な記念日に合わせた希少部位の確保
これらはすべて、生産者が直接お客様と向き合うからこそ可能なサービスです。
データに基づく品質証明
現在の流通システムでは、「美味しい」という感覚的な表現でしか肉質を語ることができません。しかし、科学的なデータに基づいて品質を証明し、説明することが可能です。
福永畜産で開示している品質データ
- MUFA値:62%(一般的な和牛は50-55%)
- 脂肪の融点:13℃(一般的な和牛は15-20℃)
- 個体識別番号による完全トレーサビリティ
これらのデータを、生産者自身がお客様に直接説明することで、真の品質をご理解いただけるのです。
業界の常識を覆す意味
「当たり前」への疑問
「牧場主は牛を育てるだけ、飲食店は料理を提供するだけ」
この業界の「当たり前」は、本当に最適なシステムなのでしょうか?
分業による効率化は確かに重要ですが、それによって失われるものの価値を考える時期に来ているのではないでしょうか。
新しいモデルの提案
福永畜産が実践している「生産者直営モデル」は、単なる事業形態の変更ではありません。畜産業界全体の在り方を見直す、一つの提案なのです。
このモデルのメリット
- 生産者の適正な利益確保
- 消費者への真の価値提供
- 食の安全・安心の向上
- 地域経済の活性化
- 持続可能な畜産業の実現
他の生産者への影響
現在、全国各地で同様の取り組みを始める畜産農家が増えています。それぞれが地域の特色を活かし、独自の価値を提供することで、日本の畜産業界全体のレベルアップにつながることを期待しています。
まとめ
なぜ牧場主が焼肉店を経営するのか
その答えは、本当に美味しい肉をお客様に届けたいという、シンプルで純粋な想いにあります。
現在の流通システムでは実現困難な以下のことを可能にするためです:
- 品質の最大限の保持
- 生産者の想いの直接伝達
- お客様との信頼関係構築
- 科学的データに基づく品質証明
- 持続可能な畜産業の実現
皆様への想い
お客様には、単に「美味しい肉」を提供するだけでなく、その肉がどのような想いで育てられ、どのような過程を経て皆様の元に届いているかを知っていただきたいのです。
そして、一口一口を味わっていただく中で、生産者の想いと技術、そして牛への感謝の気持ちを感じていただければと思います。
業界の未来への願い
このような取り組みが、やがて業界全体に広がり、日本の畜産業がより豊かで持続可能な産業になることを願っています。
「当たり前」を疑い、「本当の価値」を追求する。それが、私たちが牧場主でありながら焼肉店を経営する理由なのです。
【筆者プロフィール】 福永(株式会社牛道役員) 鹿児島県出身。1級フードアナリスト・管理栄養士・栄養教諭

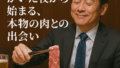
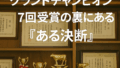
コメント