
接待での食事選びがビジネスの成否を左右することがある
接待での食事選びがビジネスの成否を左右することがある
経営者として、接待での食事選びがビジネスの成否を左右することがある——。そんな現実を、ある夜の苦い経験から学んだ話をお聞かせします。
その夜、何が起こったのか
2年前の11月、重要なクライアントとの接待がありました。相手は東京本社の役員クラス。鹿児島への出張に合わせて、地元の美味しい焼肉を味わってもらおうと考えたのです。
選んだのは、市内でも評判の焼肉店。口コミサイトでの評価も高く、「間違いない」と確信していました。予算は一人当たり8,000円程度。決して安くはない金額でした。
最初の違和感
乾杯を済ませ、特上カルビを注文しました。運ばれてきた肉を見て、私は内心で安堵しました。見た目は申し分ない霜降り具合です。
しかし、クライアントの表情が微妙に曇ったのを見逃しませんでした。
「この肉、どちらの産地でしょうか?」
そう尋ねられて、私は慌てました。事前に確認していなかったのです。スタッフに聞くと「国産和牛です」という曖昧な答え。クライアントは何も言いませんでしたが、その表情から「その程度の管理なのか」という失望を読み取りました。
決定的な瞬間
さらに追い打ちをかけたのは、肉の味でした。
一口食べたクライアントが、明らかに咀嚼に時間をかけているのです。そして、こう言いました。
「美味しいですね。ただ、もう少し柔らかい肉に慣れてしまっているもので…」
丁寧な言葉でしたが、その意味は明らかでした。「この程度の肉なのか」という失望と、「あなたの品質基準はこの程度なのか」という疑問です。
沈黙の重さ
その後の食事は、表面的には和やかに進みましたが、明らかに空気が変わっていました。私が一生懸命話を盛り上げようとしても、どこか上の空な様子。
帰り際、クライアントはこう言いました。
「ごちそうさまでした。鹿児島には素晴らしい和牛があると聞いていたので、次回はぜひそういったお店でお願いします」
その言葉の裏にある意味を理解するのに、時間はかかりませんでした。
翌日の後悔と気づき
一人オフィスに残り、その夜のことを振り返りました。
自分が犯した3つの過ち
1. 事前調査の不足 肉の産地、飼育方法、熟成期間など、基本的な情報を把握していませんでした。
2. 表面的な評価基準 口コミサイトの点数や、見た目の華やかさだけで判断していました。
3. 相手のレベルを見誤った 東京で一流の肉を食べ慣れた相手に、「この程度でも満足するだろう」という甘い考えがありました。
経営者として問われたもの
この失敗は、単なる食事の選択ミスではありませんでした。
- 品質への妥協のない姿勢
- 事前準備の徹底度
- 相手への配慮と敬意
- 本物を見極める眼力
これらすべてが、経営者としての資質として問われていたのです。
「本物」を探す旅の始まり
その日から、私の「本物の肉」を探す旅が始まりました。
最初に学んだこと
鹿児島には確かに素晴らしい和牛がある。しかし、それをきちんと提供できる店は限られているということでした。
調べていく中で、いくつかの重要な要素があることが分かりました:
生産者の顔が見えること どこで、誰が、どのように育てた牛なのか。これが明確でない肉は、どれだけ高価でも真の価値は疑問です。
科学的な品質データ 「美味しい」という感覚的な表現ではなく、MUFA値(一価不飽和脂肪酸)や熟成期間など、客観的なデータで品質を語れること。
一貫した品質管理 いつ行っても同じ品質の肉が提供される。これは生産から提供まで一貫した管理体制があってこそ実現できることです。
偶然の出会い
そんな時、地元の経営者仲間からある店の話を聞きました。
「牧場直営で、一頭買いをしている店がある。生産者が自分で店をやっているから、品質は間違いない」
初めての「本物」体験
恐る恐る予約を取り、一人で向かいました。
店主との出会い
迎えてくれたスタッフの説明は、これまで聞いたことのないレベルでした。
「本日の肉は、福永畜産で育った『さつま福永牛』です。MUFA値は62%、融点は13℃で一般的な和牛より格段に口溶けが良く…」
数値で語られる品質説明に、私は驚きました。これまでの店では「特上です」「A5ランクです」程度の説明しかありませんでした。
一口の衝撃
運ばれてきたザブトンを一口食べた瞬間、私は理解しました。
これまで食べていたものは、何だったのか。
13℃という融点の科学的根拠を、舌で実感できました。口に入れた瞬間に溶ける、まさに「とろける」という表現がこれほど的確な肉は初めてでした。
学びの連続
その夜、私は多くのことを学びました:
「一頭買い」の意味 希少部位も含めて、牛一頭を丸ごと購入することで、安定した品質と希少な部位の確保ができること。しかも牧場直営ならむしろ「一頭飼い」ですね。
「生産者直営」の安心感 誰がどのように育てた牛なのか、すべてが明確でトレーサビリティが完璧なこと。
学んだことの実践
再挑戦の機会
3ヶ月後、同じクライアントが再び鹿児島を訪れることになりました。
今度は迷わず「焼肉ギュウドウ」を選択。事前に店長から詳しい説明を受け、当日のおすすめ部位や最適なワインペアリングまで相談しました。
劇的な変化
その夜の接待は、前回とは全く違う展開になりました。
クライアントは一口食べただけで表情が変わりました。
「これは…素晴らしい肉ですね。どちらの牧場でしょうか?」
今度は私が自信を持って答えることができました。
「さつま町の福永畜産で育てられた『さつま福永牛』です。熟成させており、MUFA値は62%と一般的な和牛より格段に高い数値です」
クライアントの目が輝きました。
「ここまで詳しく説明していただけるとは。まさに本物の和牛ですね」
信頼関係の構築
その夜以来、そのクライアントとの関係は劇的に改善しました。
後日、東京での会食にも招待され、「鹿児島での食事が忘れられない」と何度も言っていただきました。そして最終的に、大型契約の締結にも至ったのです。
経営者として得た教訓
品質への妥協なき姿勢
この経験から学んだ最大の教訓は、品質に妥協しない姿勢の重要性でした。
食事の選択一つにも、その人の価値観や品質基準が表れます。クライアントは、私の肉選びを通じて、私の仕事に対する姿勢を評価していたのです。
事前準備の徹底
もう一つの学びは、事前準備の徹底の重要性です。
- 相手の好み、食べ慣れているレベルの把握
- 提供する料理の詳細情報の事前確認
- 当日の流れ、おすすめメニューの相談
これらすべてが、成功する接待には不可欠だということを痛感しました。
本物を見極める眼力
そして何より、本物を見極める眼力の重要性です。
表面的な評価や一般的な評判に惑わされず、自分自身で品質を確認し、納得できるものを選ぶ。これは経営者として、あらゆる場面で求められる能力だと気づきました。
現在の私
月2回の習慣
今では月に2回程度、「焼肉ギュウドウ」を訪れるのが習慣になっています。
接待で使うこともあれば、一人で行って大好きな部位を楽しむこともあります。スタッフの方々とも信頼関係ができ、おすすめの部位やワインペアリングについて相談できる関係になりました。
新たな発見の連続
訪れるたびに新しい発見があります。
季節による肉質の変化、部位ごとの最適な調理法、ワインとのマリアージュ。一頭買いだからこそ可能な希少部位との出会いも、毎回楽しみの一つです。
ビジネスへの好影響
この変化は、ビジネスにも好影響をもたらしました。
「品質に妥協しない姿勢」が、商品開発や取引先選定にも活かされるようになりました。また、接待成功率も格段に向上し、信頼できる店として同業者にも紹介できるようになりました。
最後に
あの失敗の夜がなければ、私は「本物の肉」と出会うことはなかったでしょう。
経営者として、品質への妥協なき姿勢がいかに重要か。そして、それがビジネスのあらゆる側面に影響することを、身をもって学びました。
もし同じような経験をされた方、または接待での食事選びに迷われている経営者の方がいらっしゃるなら、ぜひ一度「本物の肉」を体験されることをお勧めします。
それは単なる食事を超えた、価値観を変える体験になるはずです。
この記事は、実際の体験に基づいて記述しています。接待や会食での食事選びは、ビジネス成功の重要な要素の一つです。品質に妥協しない選択が、長期的な信頼関係構築につながることを、多くの経営者の方に知っていただければと思います。
【筆者プロフィール】 福永(株式会社牛道役員) 鹿児島県出身。1級フードアナリスト・管理栄養士・栄養教諭・日本箸教育講師。 25年間の学校栄養教諭経験を経て


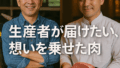
コメント