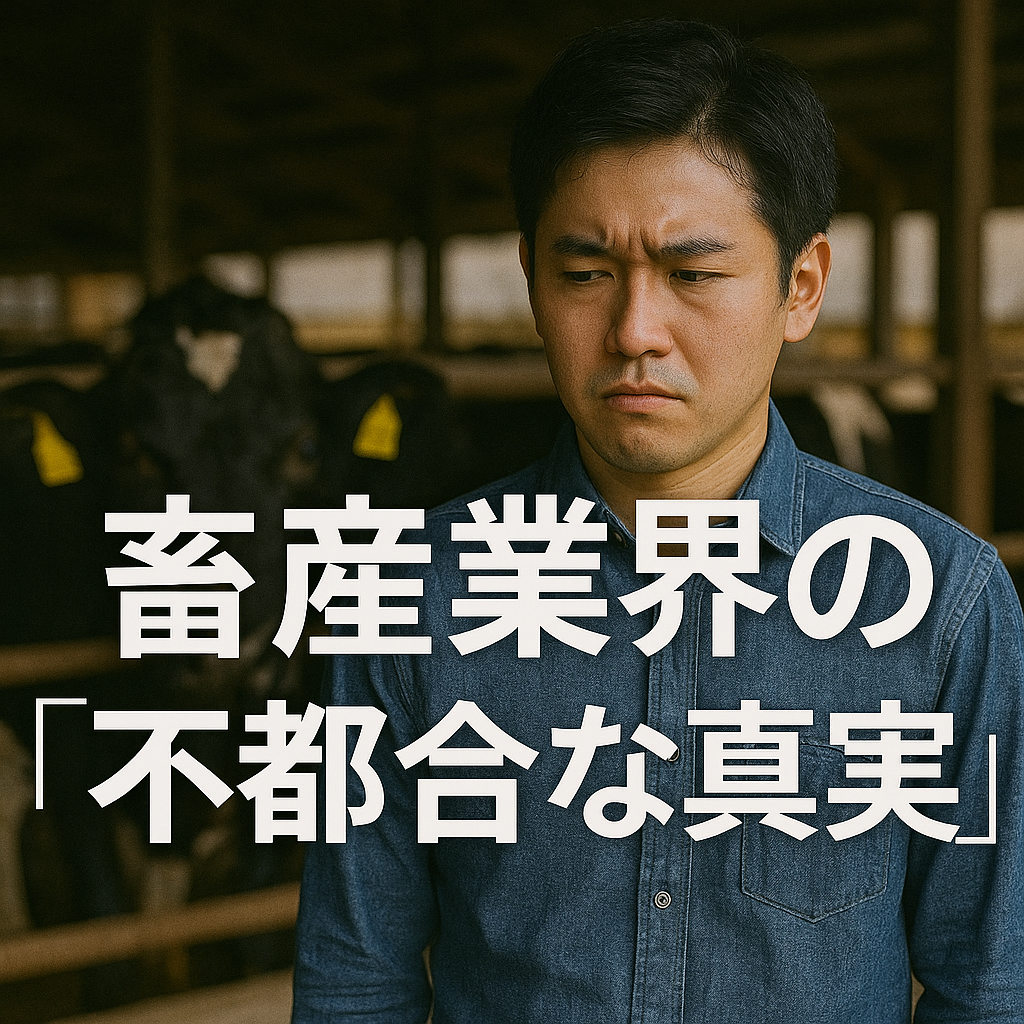
はじめに
鹿児島県さつま町で3代にわたって畜産業を営む福永畜産。その3代目である福永充氏が畜産業界で目にしてきた現実は、一般消費者が想像するものとは大きく異なっていました。
なぜ彼は既存の流通システムから離れ、市場での直接取引、直営店舗経営という道を選んだのか。その背景には、畜産業界が抱える深刻な構造的問題がありました。
今回は、グランドチャンピオンを7回受賞の技術を持ち、業界の内側を知る者だからこそ語ることができる「不都合な真実」について、客観的にお伝えします。
価格競争に巻き込まれる生産者の苦悩
「安い肉」を求める市場の現実
戦後復興期から高度経済成長期にかけて、日本の畜産業界は「いかに安価で肉を供給するか」を至上命題として発展してきました。この流れは現在も続いており、多くの生産者が価格競争の渦中に置かれています。
市場からの圧力
- 大手量販店からの値下げ要求
- 外国産牛肉との価格競争
- 中間業者による買い叩き
- 「安さ」を最優先する消費者ニーズ
生産者の実際の利益構造
一般的に、消費者が支払う牛肉価格の中で、生産者の手元に残る利益は驚くほど少ないのが現実です。
価格構成の実例(小売価格1,000円/100gの場合)
- 生産者の取り分:約150-200円(15-20%)
- 流通業者のマージン:約300-400円(30-40%)
- 小売業者のマージン:約200-300円(20-30%)
- その他(運送費、保管費等):約100-150円(10-15%)
優良生産者でも、市場取引では適正な価格での販売が困難な状況が続いていました。
品質向上への投資が報われない構造
最も深刻な問題は、品質向上への投資が市場価格に反映されないことです。
高品質化への投資例
- 高級飼料の使用:年間約200万円の追加コスト
- 熟成設備の導入:初期投資約3,000万円
- ICT技術の導入:年間約100万円のランニングコスト
- 50日熟成の実施:在庫コストの大幅増加
これらの投資により、MUFA値62%という高品質な肉の生産に成功しても、従来の流通では「A5ランク和牛」という画一的な評価しか得られませんでした。
「価格競争の罠」に陥る生産者たち
価格競争に巻き込まれた生産者は、以下のような悪循環に陥りがちです:
悪循環のサイクル
- 価格競争で利益減少
- 品質向上への投資余力減少
- さらなる価格競争に巻き込まれる
- 品質が平均化・低下
- より激しい価格競争
この結果、本来であれば素晴らしい技術を持つ生産者でも、市場からの退場を余儀なくされるケースが後を絶ちません。
品質より効率を重視する業界の現状
「効率化」という名の品質軽視
戦後の食料不足時代から続く「量の確保」を重視する思考が、現在も畜産業界を支配しています。その結果、品質向上よりも効率化が優先される構造が定着してしまいました。
効率重視の具体例
- 出荷期間の短縮化(30ヶ月→24ヶ月)※外国産牛肉は一般的に短い
- 飼料の低コスト化(栄養価より価格重視)
- 飼育密度の高密度化(ストレス増加)
- 熟成期間の短縮化(14日程度が標準)
短期的利益追求の弊害
多くの企業が四半期単位での業績を重視する現代において、畜産業界も短期的な利益追求に走りがちです。しかし、真の品質向上には長期的な視点と投資が不可欠です。
短期思考による問題
- 十分な熟成期間を確保できない
- 高品質な飼料への投資を敬遠
- 生産者との長期的な関係構築を軽視
- 技術開発への投資を後回し
「規格化」による個性の均質化
現在の畜産業界では、A5、A4といった格付けによる「規格化」が進んでいます。しかし、この規格化が逆に肉の個性や特徴を均質化してしまう問題があります。
規格化の弊害
- 格付け基準に合わない優秀な肉の過小評価
- 生産者の技術や工夫が反映されない評価システム
- 消費者の選択肢の減少
- 真の品質差が見えにくい市場構造
例えば、福永畜産のさつま福永牛のように、MUFA値62%という優秀な数値を持つ肉でも、従来の格付けシステムでは「A5ランク」という画一的な評価しか得られませんでした。
データより「感覚」が重視される取引
畜産業界の多くの取引では、科学的なデータよりも「長年の経験」や「感覚」が重視される傾向がありました。
データ軽視の問題
- MUFA値や融点などの科学的指標の軽視
- 「見た目」や「触感」による主観的評価
- 生産者の技術レベルが正当に評価されない
- 消費者への品質説明が曖昧
本当に美味しい肉が消費者に届かない構造的問題
情報の断絶問題
現在の流通システムでは、生産者の持つ貴重な情報が消費者に届かない構造になっています。
失われる重要な情報
- 個体の血統情報
- 飼育環境の詳細
- 飼料の種類と品質
- 熟成期間と条件
- 最適な調理方法
- 生産者のこだわりと想い
この情報断絶により、消費者は「本当に美味しい肉」を選ぶ判断材料を持てません。
流通過程での品質劣化
複数の業者を経由する流通システムでは、どうしても品質劣化のリスクが高くなります。
品質劣化の要因
- 長期間の輸送・保管
- 温度管理の不備
- 適切でない包装・梱包
- 取り扱い方法の問題
- 熟成中断による品質低下
特に、長期熟成を行った肉の場合、その後の取り扱いが不適切だと、せっかくの熟成効果が台無しになってしまいます。
「平均的な品質」への収束
現在のシステムでは、様々な生産者の肉が混在し、結果として「平均的な品質」に収束してしまう問題があります。
品質均質化の流れ
- 異なる生産者の肉が同一流通経路に
- 個体差や生産者の技術差が見えにくくなる
- 「平均的な品質」として市場に出回る
- 優秀な生産者の技術が正当に評価されない
消費者の選択機会の剥奪
最も深刻な問題は、消費者が「本当に美味しい肉」を選ぶ機会を奪われていることです。
選択機会の制限
- 生産者を指定した購入ができない
- 品質データに基づく選択ができない
- 熟成期間や飼育方法を選べない
- 価格と品質の関係が見えない
福永充氏が目にした現実
農獣医学部で科学的な畜産管理を学び、グランドチャンピオンを7回受賞するほどの技術を持つ福永氏にとって、業界のこれらの問題は深刻な課題でした。
「どれだけ品質の良い牛を育てても、それが正当に評価され、お客様に届けられない。この現実を変えたい」
この想いが、6次化産業への挑戦に駆り立てたのです。
海外との競争力低下
これらの構造的問題は、日本の畜産業の国際競争力低下にもつながっています。
競争力低下の要因
- 高コスト体質による価格競争力の欠如
- 品質の差別化ができない流通システム
- 生産者の技術向上インセンティブの欠如
- ブランド力の構築困難
変革への挑戦:6次化産業という解決策
構造的問題への直接的対応
福永畜産が選択した6次化産業モデルは、これらの構造的問題に対する直接的な解決策でした。
6次化による問題解決
- 生産者への適正利益の確保
- 品質情報の完全な伝達
- 品質劣化リスクの最小化
- 消費者の選択機会の拡大
- 科学的データに基づく品質評価
データに基づく品質証明
直営店舗では、従来の流通では不可能だった科学的データの開示が可能になりました。
開示される品質データ
- MUFA値:62%(業界平均50-55%)
- 脂肪融点:13℃(業界平均15-20℃)
- 個体識別番号による完全トレーサビリティ
持続可能なモデルの構築
この取り組みは、単なる一企業の事業モデル変更にとどまらず、畜産業界全体の持続可能性を高める提案でもあります。
持続可能性の要素
- 生産者の経営安定化
- 品質向上へのインセンティブ創出
- 消費者満足度の向上
- 地域経済の活性化
まとめ:真実と向き合う勇気
業界が直面する現実
畜産業界が抱える構造的問題は、長年にわたって形成されたものであり、一朝一夕に解決できるものではありません。しかし、これらの問題に目を向けず、従来のシステムにしがみついていては、日本の畜産業に未来はありません。
消費者の皆様へのお願い
この「不都合な真実」をお伝えしたのは、消費者の皆様に現状を知っていただき、より良い選択をしていただきたいからです。
消費者ができること
- 生産者の顔が見える肉を選ぶ
- 科学的データに基づいて品質を評価する
- 適正価格での購入により生産者を支援する
- 品質向上の取り組みを評価・応援する
業界の未来への希望
福永畜産の取り組みは、畜産業界に新しい可能性を示しています。生産者が正当に評価され、消費者が本当に美味しい肉を味わえる—そんな未来の実現に向けて、一歩ずつ前進することが重要です。
最後に
「不都合な真実」と向き合うことは勇気が必要です。しかし、真実から目を逸らしていては、本当の解決策は見つかりません。
この挑戦は、業界全体に問いかけています: 「私たちは、本当に消費者のために、牛のために、最善を尽くしているだろうか?」
この問いに正面から向き合う生産者が増えることで、日本の畜産業はより豊かで持続可能な産業に変わっていくはずです。
次回は、このような現実を変えるために福永畜産が取り組んだ具体的な改革について詳しくお話しします。困難な現実を乗り越え、新しい道を切り開く挑戦の物語をお楽しみに。
【筆者プロフィール】 福永(株式会社牛道役員) 鹿児島県出身。1級フードアナリスト・管理栄養士・栄養教諭・日本箸教育講師。 25年間の学校栄養教諭経験を経て。
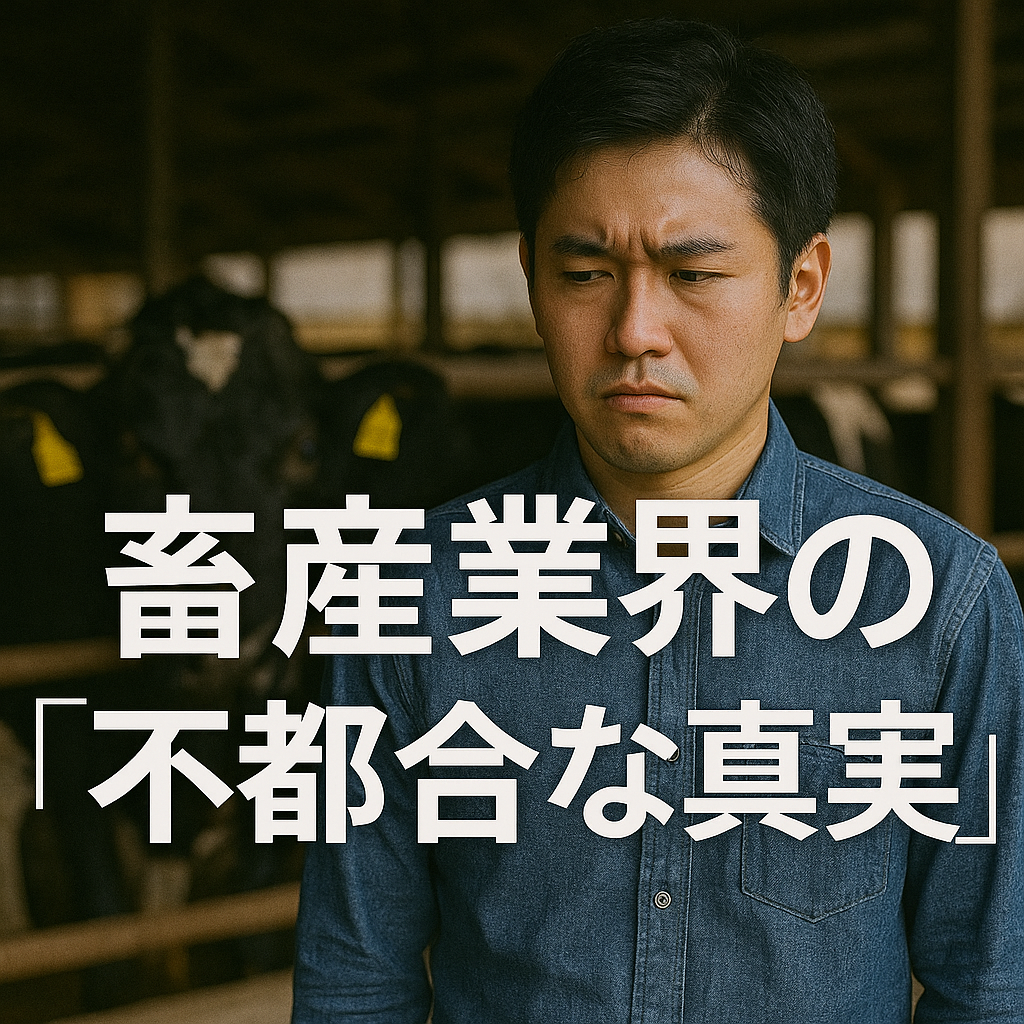
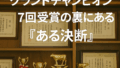

コメント